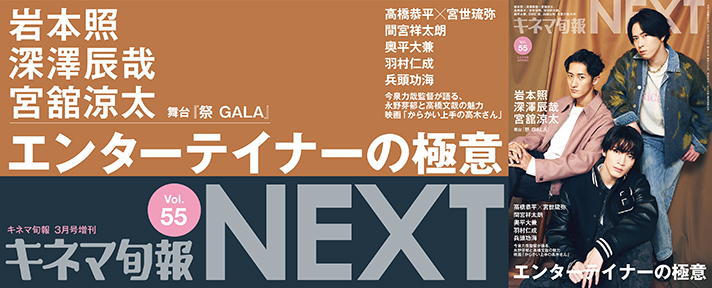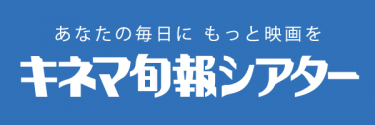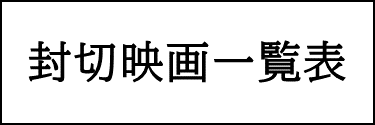ニュースNEWS
特集・評論ARTICLE
新作情報NEW RELEASE INFORMATION
週末映画ランキングMOVIE RANKING
映画ドラえもん のび太の絵世界物語
公開: 2025年3月7日 公開 7週目アマチュア(2025)
公開: 2025年4月11日 公開 2週目ウィキッド ふたりの魔女
公開: 2025年3月7日 公開 7週目片思い世界
公開: 2025年4月4日 公開 3週目ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-
公開: 2025年2月21日 公開 9週目ヤマトよ永遠に REBEL3199 第三章 群青のアステロイド
公開: 2025年4月11日 公開 2週目教皇選挙
公開: 2025年3月20日 公開 5週目白雪姫(2024)
公開: 2025年3月20日 公開 5週目ファーストキス 1ST KISS
公開: 2025年2月7日 公開 11週目ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今
公開: 2025年4月11日 公開 2週目専門家レビューREVIEW
エミリア・ペレス
公開: 2025年3月28日-
映画評論家 川口敦子
真の自分にと新たな肉体を獲得。わが子との暮らしは捨てず母性を注ぐ。暗黒街での過去の罪を悔い改めて暴力と対峙し行方不明者を探す非営利団体を組織して、その過程で新たな恋にもめぐりあう――と、望みのすべてを叶えた挙句の最期、そして聖人に?! いかにも荒唐無稽な物語をミュージカルという糖衣で包み成立させる剛腕に、でもと傾ぐ首を持て余す。「預言者」「君と歩く世界」の頃までは映画の芯に確かにあった心が見当たらないオディアールの近作、今回もまた無念を?みしめた。
-
批評家 佐々木敦
ミュージカル仕立てにする意味があるのかと観る前は思っていたが、必然性はともかくとしても曲も歌唱も極めて魅力的に仕上がっている。オディアール監督はアクチュアルなテーマとスピード感に溢れる娯楽性を高いレベルで合致させている。過去のSNS発言の炎上が何とも残念なカルラ・ソフィア・ガスコンはもちろん良いのだが、ゾーイ・サルダナが大変素晴らしい(特にあの身のこなし!)。ラストは「やはりこうなるのか」とやや残念な気もした。悲劇にしない選択もありえたのでは?
-
ノンフィクション作家 谷岡雅樹
主人公が誰かと言えば私は絶対的に弁護士だと思うのだ。だが、タイトル名でもある麻薬王で犯罪者のその人物の、第二の人生という、圧倒的なパフォーマンスによって、人権派と思しき弁護士も、その助力者となり突っ走る。そして第二の人生を受け入れず意のままにはならぬ元妻。三人は、それぞれの折合いをどう付けて生きていくのか。♪いつまで奴らに媚を売るの。いつまでこき使われるの。心の声が歌になる。造形物でもって人生の改革は難しい。絡まった運命の鉄鎖のもつれを、三者三様ほどいていく。
ベイビーガール
公開: 2025年3月28日-
映画評論家 鬼塚大輔
「ナインハーフ」、はたまた「フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ」かと思っていると「危険な情事」に……、と特定ジャンルに収まらないまま物語が進んでいくのがむしろ魅力の作品。善か悪か、被害者か加害者か、と単純化できないヒロインをキッドマンが熱演。かつてのセックスシンボル、アントニオ・バンデラスをこの役で使うというのも、「昼下りの情事」でモーリス・シュヴァリエにうらぶれた探偵を演じさせたワイルダーのイジワルさを想起させて面白い。
-
ライター、翻訳家 野中モモ
よくある話の男女逆転? なんてことないエロティック・スリラー? しかしこの「なんてことなさ」こそ女たちが獲得しようと苦労してきたものなのだろう。「サブスタンス」のデミ・ムーアもそうだったけど、洋画が好きな自分はある意味ずっと「ニコール・キッドマン物語」を見てきたんだな……と思い知らされて感慨深いものがある。だって「誘う女」も「ある貴婦人の肖像」も「アイズ ワイド シャット」も伏線になるわけだから。音楽がどこかふざけてる感じなのも「あえて」の深刻の回避とみました。
-
SF・文芸評論家 藤田直哉
女性CEOがインターンに誘惑され、秘められていたSM的欲望を解放していく。よくある官能映画・ポルノの導入だが、組織内で女性が「権力」を持っているが、プレイや関係においては従属であるという厄介な問題を真正面から描いた点に好感。立場や家庭があるから「ダメ」と思いながら、誘惑に惹かれていく分裂した女性の演技をニコール・キッドマンが実に見事に演じている。SM的な欲望をどうしても抱いてしまうことをどう受容するかという物語の側面には感動させられた。
山田くんとLv999の恋をする
公開: 2025年3月28日-
映画評論家 上島春彦
エンドクレジットの後に映画最高の瞬間が訪れるのに、見ないで出ていった愚か者がいた。山下美月ファン必見。私なんかファンでもないのに大感激である。作間龍斗ファンは複雑な心境か。ただ主人公が美女すぎて、そうなるとあざとさが前に出ちゃう感じがする。恋愛未満の感情を扱う作品なんだから作間の同級生茅島みずきにだって山下と同じ資格はあるのに、あんまりハラハラさせてくれないんだなあ。ほっこりできる好企画で推薦できるが、傍役陣は主人公を守り立てるだけの役割なんだね。
-
ライター、編集 川口ミリ
人気少女漫画を原作に、トップアイドルを主演に迎え、誰もがときめくラブコメを撮る。その初ミッションを、安川監督は丁寧にやり遂げた。印象的なのは、主人公たちがまだ不確かな想いを不器用に伝え合う文化祭シーン。ダイアローグをふまえての、階段を用いた俳優同士の位置関係が絶妙で、その位置設定が別シーンでも反復され生きてくる。微かに届く吹奏楽部のチューニング音により、恋のはじまりを予感させるセンスにも唸った。色使いにも工夫が見られ、ゲームチックなギミックも楽しい一作。
-
映画評論家 北川れい子
20歳の女子大生が、ネトゲで出会った男子高校生にお熱を上げましたとさ。ラブコメ好きの若い世代向けに作られた作品だが、にしても主人公の幼稚さ、能天気さにはほとほとマイッタ。言動やナリフリはまんまギャルで、彼女の部屋はカワユイのてんこ盛り、そのくせ酒にはだらしない。演じている山下美月も、高校生役の作間龍斗もすでにしっかり大人顔だけに尻がムズムズ。「よだかの片想い」の安川監督の演出も過剰にハシャギ過ぎ。でも原作ファンにはいいのかも。
ミッキー17
公開: 2025年3月28日-
映画評論家/番組等の構成・演出 荻野洋一
MCU的マルチバースで惰眠を貪るアメリカ映画を全否定する映画である。ポン・ジュノは今回、「パラサイト」と「グエムル」を合体させ、何度も殺されては蘇生させられる最下層の男の悲哀と反撥の火種を通じて、映画人たちが胡座をかくマルチバース的全能感を告発し、さらにはファシストを打倒するため、いま一度、黒人女性のリーダー像を擁立する。第二次トランプ政権の誕生を予知した上で、「スターシップ・トゥルーパーズ」的ニヒリズムと戯れていればよい時代の終焉を宣言したのだ。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
中盤までふざけまくってて面白かったが、肝心の「何が揃えば〈私〉になるのか」ってハードな哲学がどっかにいき、16回死んでも残ってた罪悪感を分身がぬぐうセラピー的よくある話になったのが惜しい。シリーズ化できぬものを金かけて作る心意気は買えるが、つい「インターステラー」と比べちゃうな。あっちのほうが男のロマン臭かったのにSFギミックの使いかたが上手で、謎に感動させられたよね。それにしても今後ハリウッドはトランプをいつまで風刺できるのか。がんばり続けてほしいのだが。
-
著述家、プロデューサー 湯山玲子
再生医療の極致である「生き返り」が可能になった世界で、そういう存在が重宝されるのは、人体実験だろうなぁ、という悪い予想そのままの主人公が、運命を案外淡々と受け入れるやるせなさ加減には、さすがこの監督ならではの、弱者のリアル描写とブラックユーモアが光る。しかし、後半になるとそのテイストが失速。主人公の敵となる宇宙船の支配者夫婦の描き方が、カリカチュアされすぎだし、先住者であるデカい芋虫系生物の在り方も紋切り型で凡庸な勧善懲悪劇になってしまった。
BAUS 映画から船出した映画館
公開: 2025年3月21日-
評論家 上野昻志
青森で活動写真の魅力に嵌まった兄弟が上京して、ひょんなことから、東京の郊外、吉祥寺の映画館「井の頭会館」で働き始めた1927年から、ムサシノ映画劇場を経てバウスシアターになるという、かの名物劇場の90年に及ぶ歴史を、兄弟を巡る家族の物語に重ねて語っていく。もともとは、青山真治が書いたシナリオを、甫木元空が改稿・監督したものだというが、冒頭に示される老人の回想というかたちにしたことで、どこか夢物語ふうな色合いを帯びることになった。
-
リモートワーカー型物書き キシオカタカシ
「逃走」にて居直ったかのように現代の風景がそのまま映し出されるたび現実に引き戻されてしまったのだが、限られた予算で“歴史”を描こうとすれば物理的アナクロニズムが避けられない。本作も制約の中で工夫を凝らしているものの限界は明らか。しかし逆に一種の異化効果と言うべきか、過去と現代がオーバーラップした存在として立ち上がる作用が生まれていた。過去からの想いを受け取り、その普遍性を今のものとして瑞々しい感性で語り直す――そんなタイプのアナクロニズムは大歓迎。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
活動家ではなくカツドウ屋しか出てこないけれど、映画を観ることも生活することも、すべては政治的な営みだという姿勢が全篇を貫く。そのまま朝ドラの題材にスライドできそうな物語にエッジが立つのはそのためであり、しかも出てくる人々は、たいして背景が描きこまれているわけでもないのに、みな熱い血がかよっている。そして驚くべきは、この映画がまぎれもなく甫木本監督の演出力を証明するものでありながら、なお青山真治の存在を強烈に感じさせることだ。この監督の早世があらためて惜しまれる。
その花は夜に咲く
公開: 2025年3月20日-
映画評論家 鬼塚大輔
いや、これは主人公カップルの片方をトランスジェンダーにしなくても成り立つ古臭い話ではないのか?と思って観ていると、途中からもう一人(二人?)が加わって、性別/性差を超えた小さくとも理想的な共同体の成立と崩壊の物語として奥行きが出てくる。いくつかの点で「エミリア・ペレス」を想起させるのも、二つの作品を合わせて考えると興味深い。ヴェトナムの街並みをしっとりした触感で捉えた撮影も魅力的で、作品世界の中に引き込まれていく。
-
ライター、翻訳家 野中モモ
ナイトクラブで歌うあでやかな姿も、化粧を落とした自宅での姿も、主人公を演じるチャン・クアンが本当に美しく撮られているのが見どころ。ちょっとIS:SUEの釼持菜乃に似ているし、往年のナスターシャ・キンスキーや満島ひかりを思わせる瞬間もあってまさに「なりたい顔」。社会の周縁に生きる若者たち(というかほぼ子ども)が肩寄せ合って疑似家族を築く中盤はある種の少女漫画に通じる味わいがあって引き込まれたが、悲劇に向かう展開はあまり好きになれなかった。
-
SF・文芸評論家 藤田直哉
魅力的で壮麗な衣裳や美術で現代ヴェトナムが活写されており、ハッとさせられるような都市描写が幾度もある。貧困な若者が格闘家になったり、トランスジェンダーの女性たちが身体を売っており、富裕層との描き方の差、彼らの精神的な苦しさの描写には胸が詰まる。が、どうも肝心のドラマが弱い。対立と葛藤がはっきりと顕在化しないような個と関係性の社会だからこそ中盤の関係性になったのかもしれず、そこは良かったのだが、それをもう少し掘り下げてほしかった。
教皇選挙
公開: 2025年3月20日-
映画評論家 川口敦子
90年代グッド・マシーン社でA・リーやT・ヘインズにつき修業した監督ベルガー。その佳作「ぼくらの家路」(14)は、R・ハリス原作の新作とはまた別の世界を描きながら、目の前の困難に耐える少年を無駄口叩かずみつめる眼差しが、ヴァチカンの閉塞的時空で欲望と陰謀渦巻く教皇選挙の現実に耐えるひとり(R・ファインズ適役!)を活写する様と重なり面白い。70年代A・J・パクラの政治的スリラーを意識したという今回も不安を抱え耐える存在への共感がふるふると映画を活かしている。
-
批評家 佐々木敦
レイフ・ファインズ演じるローレンス首席枢機卿がバチカンに急遽やってくる冒頭のシーンを除き、映画はシスティーナ礼拝堂の敷地内を一歩も出ない。コンクラーベを巡る思惑と策謀。繰り返される投票が静かなサスペンスを生むが、広大な密室劇の「外」を開示するある出来事以降、物語は大きく転回する。ファインズをはじめとする俳優陣の重厚な演技、監督ベルガーの手堅い演出も見事だが、これはピーター・ストローハンのシナリオの勝利だろう。一種の宗教論とも呼ぶべき作品だと思う。
-
ノンフィクション作家 谷岡雅樹
映画には作者の主張が滲み出る。対立する候補がいても、言い分を並列に描いても、そこには作家の態度が現れる。理想を捨ててはならない、という主張の人物こそ際立つ。103人という多人数でもって、人間模様を映し出し、善悪の境界を微妙に群像配置する。右往左往し逡巡する集団の様を俯瞰で捉えた洪大な映像で見せる。脚本家は「裏切りのサーカス」よりまた一つ権力闘争を心で紡ぐ点描図。選挙には不純物が混じる。形勢は刻一刻変転する。点である個々の人間の動線。これこそがまさに映画だ。
悪い夏
公開: 2025年3月20日-
映画評論家 上島春彦
原作の毒を映画に期待した人には物足りない脚色かもしれないが、私はこれが功を奏したと思う。河合優実を刑務所に送らないですむように処理したわけだ。また原作で唯一の被害者である母子も映画では死んでいない。ここも重要。やみくもに倫理観を振りかざす伊藤万理華の口元が徐々にひん曲がっていく印象で実に可笑しい。嵐の晩に関係者が一堂に会するクライマックスがスラップスティック喜劇感覚で最高だ。それにしても北村匠海がこんなにいい役者だとはこれまで知らなかった。
-
ライター、編集 川口ミリ
生活保護制度を巡って渦巻く人々の欲望。そんなただでさえドロドロとした物語が、クローズアップを多用してグロテスクに描かれており息が詰まる。アプローチが安直すぎるのでは。演技にも同じことが言える。城定監督はきっと俳優を乗せるのがうまいのだろう。それは諸刃の剣で、今回はクレイジーに振り切った芝居ばかり見せられ残念に思った。その中でシングルマザー役の河合優実、木南晴夏は光って見える。彼女たちの、役の尊厳を損なわないレイヤーのある人物解釈が本作の救いだ。
-
映画評論家 北川れい子
さして珍しくもない貧困ビジネス。描き方次第ではいくらでも社会派映画になる。がこいつら全員ロクでなしと、冷酷な遊びを盛り込んで容赦なく追い詰めていく向井康介の脚本と城定秀夫監督にシビレた。どいつもこいつもザマアミロ! スケールは異なるが、ちょっと韓国の露悪的犯罪サスペンスに似てるかも。同情と善意と弱気の三つ巴で貧困ビジネスに加担せざるを得なくなる職員役の北村匠海も、無気力にふてくされた河合優実も、笑えるほど実感があり、いや笑った。
少年と犬(2025)
公開: 2025年3月20日-
映画評論家 上島春彦
馳星周がこういう原作を書いているとは驚いたが、私が無知なだけでした。瀬々敬久の毒々しさと抒情性を兼ね備えた演出、そして連作をうまいこと一本化した林民夫の脚色もいい。宣伝だとネタバレ厳禁なので『名犬ラッシー』調の企画と思われそうだが、見れば分かるように、迷い犬の多聞をどこまでも追ってくる高橋文哉が鍵となる。しょっぱな、多聞はガーディアン・エンジェル(守護天使)と規定されるのだが、高橋も西野七瀬の守護天使なんだね。西野が××嬢ってのも驚きの好配役。
-
ライター、編集 川口ミリ
原作の淡々とした筆致とは異なり、映画はコミカルに幕を開ける。高橋文哉演じる主人公が陽気な語り部となるのだが、訳ありとはいえ闇バイトに手を染めた彼に、ここまで倫理的な葛藤や切迫感がなくていいのか。諸社会問題はもはや物語を進行するための駒でしかなく、後半は感動ポルノ的なドラマへと強引に転調する紋切り型の流れ。各キャラは薄っぺらで、ショットもなんだか味気ない。ただ多聞に扮する、シェパード犬のさくらはナイス配役。憂いをたたえた瞳にほとんど唯一、役の深みを感じた。
-
映画評論家 北川れい子
この映画における犬の多聞は主役というより世相や時代を描くための狂言回し的。いや、それが悪いわけではないが、多聞が出会ういずれも孤独な人々のエピソードが重すぎて息苦しいことも。特に西野七瀬のパート。多聞は森の中での彼女の異様な行動を静かに見ている。これって、ここ掘れワンワン? が彼女はとんでもない秘密を抱えていて、しかも多聞、危うく彼女に殺されそうに。南を目指す多聞が横切る四季それぞれの叙情的映像は効果的だが、へヴィな美談である。
逃走(2025)
公開: 2025年3月15日-
評論家 上野昻志
桐島聡とは誰か? 1974?75年に三菱重工本社ビルの爆破をはじめ、企業を連続爆破した東アジア反日武装戦線内のさそりのメンバーで、他グループを含め大半が逮捕されたなかで、ただ1人、逃げおおせた男だ。本作は、山中で、爆弾の威力を確かめる若き日の桐島たちの行動から始まるが、主題は、他人になりすまして官憲の手を逃れた桐島の49年間を問うところにある。自問自答を繰り返す桐島を演じた古寛治がいい。そこから、彼にとっての逃走が闘争であったことが浮かび上がる。
-
リモートワーカー型物書き キシオカタカシ
多くを語らず死去した桐島聡本人の内心は想像しかできず、どのようにも創造し直すことができる空白のキャンバスである。ここでその“空白”に注入されているのは監督の半生……本作は桐島聡の伝記である以上に足立正生の半自伝と言えるだろう。オリヴァー・ストーンが乱発していたような“他人の人生をハイジャックした実質的自伝映画”は時に問題を孕む。しかしこの余人に作れない作家性の煮凝り・総決算には、かつて若松プロの映画にハマっていた内なる大学生が拍手喝采させられた。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
桐島聡の逃走=闘争=労働の日々。熱い思いを描きながらも、形式とスタイルは意外にクール。1970年代に存在していた物品だけをそろえて時代を再現するのは難しかったように見える前半部には、演劇的な抽象性の面白さがある。若き日の桐島は、日雇い仕事をしながら現実社会のシステムを学んでいるかのようだ。古寛治に交代してからの壮年以後の彼は、社会の激変に立ち会いつつ、自己批判と内省を繰り返す。現実とも幻覚とも知れぬシーンとの交錯により、抽象的な前半とのトーンの整合性も保たれる。
私たちは天国には行けないけど、愛することはできる
公開: 2025年3月14日-
映画評論家 川口敦子
ポケット・ベル、公衆電話、「好き」を伝える手書きの手紙。アナログな光景が「世界の終わり」を待つ1999年、少女の夏を息づかせる。カラオケの時間、くぎ付けになってしまうひとりへの想いが、くぎ付けの視線を浴びるひとりにも伝わって解ける初恋、そのときめき。それが同性への気持ちであってもそこに逡巡はない。そんな青春の物語のみずみずしさに世紀末韓国高校スポーツ界に巣食う暴力、腐敗を突くサブプロットのどす黒さが食い込んで虻蜂取らずの印象に堕すのが惜しい。
-
批評家 佐々木敦
「はちどり」「イカゲーム」という大ヒット作の脇役だった二人の主演女優は良いし、テコンドーという道具立ても意外性があるのだが、うーむ、作劇的に見ると紋切型と御都合主義が否めないのじゃないかなあ。少女同士の恋愛を中心に置いて、権力勾配やいじめや格差や偏見などといったテーマを縦横に配しているのだが、結果としてどれも掘り下げがいまいち足らないように感じてしまった。タイ映画の佳作「ふたごのユーとミー 忘れられない夏」も1999年を描いていたが、何かあるの?
-
ノンフィクション作家 谷岡雅樹
テコンドーの指導者により、選手たちは虐待されている。5日間で6キロ増やせ。八百長しろ。性加害まで受ける。親は、不正を見逃しお金を貰えという。弱い立場の者は我慢して権力者には屈しなければいけないのか。これを対岸の火事と笑い、無関係と非難できるのか。主人公の前に現れるのは天使であり異物のような救世主だ。だが、より深い現実に絶望している。今度は、主人公が天使となる番だ。悪はそれ自体でこちらの世界の愛を汚すことはできない。殻を破り、日常に裏打ちされた心は、汚されようがない。
ドマーニ! 愛のことづて
公開: 2025年3月14日-
映画評論家/番組等の構成・演出 荻野洋一
イタリア社会が家父長制とジェンダー的不平等に立脚していたことを告発した点、そして社会性とエンタテインメント性を両立させて国内No.1ヒットを果たした点は、評価に値する。しかし、ここに写っているローマ市民はスタジオに配置されたノスタルジーの書割にとどまる。また、主人公が夫からDVを受けるシーンで音楽に合わせた振付をほどこしてミュージカル仕立てとしたのは致命的な誤りだ。この様式化によってフェミニズムの訴求性が減衰し、エンタメとして消費されてしまった。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
ぜひ多くの女性にもDV男にも観てもらいたい良作なんだが、ラストのオチが今年観るとちょっと複雑。民主主義や参政権が機能してるからこそ世の中が変になってるって驚くべき時代に我々はもう突入しちゃっているからね。なぜ彼女は自分を殴るようになる男を好きになったのか、などと通俗心理学で分析してもフェミニズムは達成できぬ、そんな暇があったら殴られてるのをまず止めたいと僕も思うけど、しかしやはり映画としては「ナミビアの砂漠」のほうが面白いんだよなあ……、映画としてはね。
-
著述家、プロデューサー 湯山玲子
日本でもお馴染みの家父長制男尊女卑社会も、所変わればそのテイストも変わる、 というわけで、戦後間近のイタリア、下流の人々のそれは、キリスト教の影響も相まってハードコア。主人公及び登場人物の女性たちの怒りの解決が、実は社会システムにあり、という点がこの作品の思い切った切り口。トランプ大統領時代になった今、本作の民主主義肯定感は貴重。紋切り型の女同士の連帯モードを使わず、市井の女性の理不尽を生きる現実感を描写したネオリアリズモにイタリアの伝統をみた。
スイート・イースト 不思議の国のリリアン
公開: 2025年3月14日-
映画評論家 鬼塚大輔
さまざまな怪しい団体やカルトがうごめく“不思議の国”アメリカを、したたかにノンシャランと突っ切っていくヒロインの姿をざらりとしたタッチで描く映像が実に魅力的。ヒロインとロリコン教授の関係は、アリス・リデルとルイス・キャロルの関係が下敷きだよねとか、ポー、グリフィス、そしてモリコーネまで登場とか、実に賑やかで楽しい。製作総指揮がティール財団(ググってください)の元専務理事だと知ってしまうと作品の見方ががらりと変わり、ラストがさらに怖くなる。
-
ライター、翻訳家 野中モモ
ヒロインの首を彩るタトゥーチョーカーとスケーター風のスタイリングに「時代設定は90年代?」と思ったらスマートフォンが出てきた(そしてすぐに使えなくなった)。刹那的に状況に流され続けてしまうのも、構ってくる男がことごとくクズなのも、たぶん誇張と戯画化を施した今のアメリカの現実で。先日グレッグ・アラキ監督「ドゥーム・ジェネレーション」のリバイバル上映を観て、こういうデタラメかつ切実な冒険ものが今の世の中には不足している! と思っていたところにグッドタイミングの公開。
-
SF・文芸評論家 藤田直哉
ノスタルジックな少女趣味の画調と衣裳でヒロインの魅力を写しながら、アメリカン・ニューシネマを思わせる撮影方法や編集と旅で、現代アメリカのさまざまな政治的問題や集団を次々に見せる、野心的な作品。懐古的な画面と衣裳と女性の美の描き方なのに、オルタナ右翼の陰謀論・ピザゲート事件を思わせる事件から物語が転がり出す。ジャンルや時代を錯誤した独自のハイブリッドなスタイル自体が、過去志向と未来志向の混濁する現代アメリカに即した批評性を発揮し見事。
早乙女カナコの場合は
公開: 2025年3月14日-
評論家 上野昻志
まず、少女マンガもかくやという出だしに、先行きが心配になる。それも、演じている男女が、大学生というには、いささか薹が立っているかに見える(失礼!)からだ。もっとも、その点は、彼女や彼が、この時から先、6年後までを生きるという物語の要請故だろう。その時間の中で、カナコを中心とする女性たちが、男たちの単純さとは裏腹に、恋愛を真剣に考えていくさまは悪くない。ただ、彼らの世界が、それだけで閉じられているかに見えるのは、現代日本を反映しているためか?
-
リモートワーカー型物書き キシオカタカシ
“東京私大の擬人化”的な若者の多視点から描かれた小説。それに対し、そんなステレオタイプを意識的に排除して直球な恋愛10年史に仕立て直した映画。“悪しき固定観念の助長を避ける”という切り口には頷けるのだが、本作の場合は登場人物の自意識こじらせの大部分もまた切り捨てられることに。時には過剰な戯画こそが真髄を突くこともあるのかもしれない。映画で軸となるユスターシュと原作における「カリ城」のトレードオフなら後者にリアルを感じる個人的趣味の問題もあるが……。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
紋切り型が(たぶん意図的なのだろうが)連続する前半は、この演劇サークル全然公演を打ってる様子がないけど大丈夫なのかとか、どうでもいいことばかり考えてしまったが、山田杏奈演じる学生が虚飾をかなぐり捨てたところから、シスターフッドが前面化して急に面白くなる。最後に突然言語化される、男社会での男の生きづらさの問題は、もっと早い段階から多角的に掘り下げてほしかったと思うけど、音楽の使用に対して極端に禁欲的であることも、顔のクロースアップすべてに存在感があるのも好ましい。
Flow
公開: 2025年3月14日-
映画評論家/番組等の構成・演出 荻野洋一
この動物アニメは痛烈なディズニー批判としてある。この冬は「ライオン・キング ムファサ」の自堕落な擬人化描写に辟易とさせられた。人間界の自分本位な問題系を野生動物に転嫁する傲慢さ。ハリウッドアニメは擬人化の病から逃れられそうもない。いっそ「すずめの戸締り」の新海誠のように椅子を擬人化した方がまだ刺激的である。一方、ジルバロディスは動物を動物としてしか撮らない。人間の痕跡は人類文明終焉後の廃墟としてのみ提示する。私たち人類に観念の行き先を迫る作品である。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
擬人化のぐあい、リアルさのころあいが僕にはちょうどよかった。自分がいかに「動物が言葉の世界で生かされてる映画(動物をダシにした映画)」が嫌いかがわかった。言葉をもたざる者たちは、人間が滅亡して言葉を使う者が誰もいなくなってから、どんなチームを組んでどんな冒険をし、どんな神話に救われて、どんな夢をみるのか。言葉でしか世界を把握できない我々は言葉を使わないと映画のシナリオも書けない阿呆だ。マジで我々はそろそろ絶滅しても大丈夫だと思った。あとは動物に任せよう。
-
著述家、プロデューサー 湯山玲子
ナポリ沖バイアの水没遺跡や、水の都ヴェネチアのダントツ人気等、水の驚異と美しさというものは、身体感覚的にも情動的にも私たちを強烈に魅了するが、そこにアニメ表現がド正面から挑んだ凄い作品。ノアの箱舟状態の船に、主人公の黒猫や犬、トリ、猿、カピバラが文字通り呉越同舟するのだが、収集癖、群れ欲求などの生物的習性を越えて、仲間になっていく姿に、宇宙船地球号っぽい多様性共存のロマンを感じさせるところもナイス。動物たちの擬人化、必要最小限のバランスも上手い。
フライト・リスク
公開: 2025年3月7日-
映画評論家 鬼塚大輔
トランプによって映画特使に任命されたメル・ギブソンがハリウッドの操縦桿を握るというのには(他2名の人選も含め)米映画界にとってリスクしか感じられないが、ガッチリとした演出の中にトレードマークである人体破損と執拗な暴力をしっかり入れ込んでくるあたり、監督としての力量は確かだ。マーク・ウォールバーグは、ひさびさとなる悪役を気持ち良さげに演じているが、これはやはりギブソンが自分で演じていれば、もっと面白く、さらに怖くなったはず。
-
ライター、翻訳家 野中モモ
「こういうの90年代によく観た気がする」コンパクトなアクション映画。眼下に広がる雪と氷に覆われたアラスカ山脈は劇場の大画面に映えることだろう。そのうえ4DX上映もあるの!? 同じ作品でも鑑賞する環境次第でまったく違う体験になりそうだ。主な登場人物3人のうち最もヒロイックに銃を構える役が女性に配されているあたりは今世紀の作品らしい。とはいえメル・ギブソンがゴリゴリの宗教保守として問題行動を重ねてきたことを思うと、頭を空っぽにして楽しもうとしても苦みが残る。
-
SF・文芸評論家 藤田直哉
これまでの、こってりしたメル・ギブソン監督作品は嫌いじゃないのだが、今回は不発。軽飛行機の中、主要人物は三人だけ、リアルタイムに近い時間の流れで、緊急事態に観客を臨場させようとするのは分かるし、面白いが、物語の展開に驚きが乏しかった。なにより、全体を通した(現代の政治状況を思わせる)「不信と信頼」の主題系に対する落とし前、解決策の提案がないのがあまりに殺風景で、投げやりな印象を受ける。荒涼と孤独こそが現在の実存的リアルだとしても。
Playground/校庭
公開: 2025年3月7日-
映画評論家/番組等の構成・演出 荻野洋一
ベルギーにおけるいじめを描くが、マスターショットを除外し、主人公のヨリだけをフォローしていく。なぜこんなにダルデンヌ兄弟の真似をしようと思ったのだろう。そこに何が生起しつつあるかよりも、主人公にどう見えているかのみを追求する姿勢は、ひとつの見識ではある。ただし流行りの被写界深度浅めのルックは対話の余地も発見の細部も遮断し、単一方向へと頑迷に流れるのみ。カメラの切り返し、精神の切り返しが重要だ。ゴダールの画面も被写界深度浅めだったが、切り返しが主役だった。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
子役の演技が達者な映画を観ると、いつも「すごいな」と思いつつ「大丈夫なのかな」とも感じてしまう。外国語の映画を観ると、上手に見える演技(子役にかぎらず)が的確なのかどうかがネイティブでない僕には本当にわかってんのかなといつも疑ってしまうが、この映画の子役はすごい。ますます「大丈夫なのかな」と思う。あと映画と現実ということも考えてしまう。ほんとは子どもたちに観てほしい映画なのだが、観せられる機会は少ないだろう。こういう映画をなんとか学校で上映できないものか。
-
著述家、プロデューサー 湯山玲子
学校という閉じた空間の中で、子どもたちが社会性とそれとは無関係ではない“悪”を、恐怖や不安を発火点に経験していくさまは、ルソーの教育論『エミール』の合わせ鏡のよう。特筆すべきは映画全体を覆うかなりの音量の子どもたちが発する自然音BGMで、それすなわち、彼らのエネルギーの強さと生命力を表徴。この体感的な演出も含め、子どもの世界特有の理性&思惑なしの言動を、細部にわたり見事に映画に喚び活けている。お兄さん役のギュンター・デュレの暗い色気は、今後要チェック。
スケジュールSCHEDULE
 映画公開スケジュール
映画公開スケジュール
- 2025年4月18日 公開予定
-
アイニージューデッド!
トロマ・エンターテインメントでロイド・カウフマンのもと、修行を積んだジャンル映画期待の新星ロコ・ゼベンバーゲンによる初長編。予算もないなか、初めてメガホンを取る監督がギリギリの状況で制作を進めるが、様々な困難が生じてゆく顛末を描くホラーコメディ。ロコ・ゼベンバーゲンが初の映画制作に悩む監督という自身の境遇と重なる役を演じるほか、ロイド・カウフマンがカメオ出演。 -
あて所に尋ねあたりません
仕分け倉庫で働く不器用な女性が離職する同僚に手紙を渡そうと奮闘する短編ドラマ。監督・脚本はたかはしそうた。出演は神田鯉花、樋之津琳太郎、山崎陽平、やす(ずん)、中島ひろ子。次代を担う若手映画作家を発掘・育成する文化庁の日本映画振興事業「ndjc2024」完成作品。 -
あわいの魔物たち
空き家となった実家へ夫と帰省した女性が、連れてきた愛犬の失踪に戸惑う短編ドラマ。監督・脚本は守田悠人。出演は中村映里子、遊屋慎太郎、外海多伽子、安藤馳隼、銀牙ほか。次代を担う若手映画作家を発掘・育成する文化庁の日本映画振興事業「ndjc2024」完成作品。
 TV放映スケジュール(映画)
TV放映スケジュール(映画)
- 2025年4月16日放送
-
13:00〜15:06 NHK BSプレミアム
アパートの鍵貸します
-
13:40〜15:40 テレビ東京
ゴシカ
-
19:00〜21:00 BSジャパン
プレデター2
-
20:00〜22:03 BS松竹東急
ゴジラVSモスラ
- 2025年4月18日放送
-
13:00〜15:00 NHK BSプレミアム
リオ・グランデの砦
今日は映画何の日?
今日誕生日の映画人 4/15
- エマ・トンプソン(1959)
- メイジー・ウィリアムズ(1997)
- トーマス・F・ウィルソン(1959)
- エマ・ワトソン(1990)
- ルーク・エヴァンス(1979)
- ジョジアーヌ・バラスコ(1950)
- 嵐ヨシユキ(1955)
- 北山雅康(1967)
- 須間一彌(1965)
- オルガ・ボゴリューボア(1954)
- セルゲイ・ブスケバリス(1966)
- 佐藤賢一(1970)
- ワン・ビンナ(1982)
- イ・ジュナ(2001)
- 原田楊子(1967)
- 刹奈紫之(1975)
- JOY(1985)
- リッカルド・ミラーニ(1958)
- 田代絵麻(1985)
- 柴浩二(1989)
- エスター・ディーン(1982)
- ウォルター・F・パークス(1951)
- ダン・タイン・タム(1964)
- 野口聡一(1965)